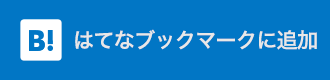【ソフトボール解説】ピッチャーの完全停止って2秒以上5秒以内

この記事の目次
前回の投稿後、また少し調べてみました。
あいまいな判定のわけは
「ルールブック」「ケースブック」の他にもう一冊日本ソフトボール協会が発行しているものに、「競技者必携」があり、その中に何か記述があるかと探してみましたが、どうもこのことについては触れられていないようです。
となればと日本ソフトボール協会に電話して聞いてみることにしました。結局はそこに書かれている通りであり、現場では審判員の判断に任せられているようです。困るのはその基準がまちまちになるってことです。判定の統一がされていなければ、ある時には「不正投球になり」、ある時には「不正投球にならない」が一つの大会に混在するということになります。
こんなことはピッチャーには、昔からよくあることです。例えば「ジャンピング」この取扱いも変遷を重ねてきました。今はルールの改正で「ジャンピング」「ツーステップ」も認められましたが、以前は完全に禁止されていました。その前は曖昧な判定のおかげで、跳んでいるピッチャーもたくさんいました。審判が「イリーガルピッチ」を宣告しなければ大丈夫だったんです。
一説には、予選を通過してきているのだから、本大会(全国大会)で「イリーガルピッチ」とするわけにはいかないというのが、現場での不文律だみたいなことを聞いたこともあります。
ただ大会も進行して、それまでは何も言われなかったものが、ある試合の特定の審判員が突然「イリーガルピッチ」を宣告する場面がありました。これは承服しかねる判定でした。今までセーフだったものが、突然ダメと言われても対応のしようがありません。
ルールは守るためにあるもの
ルールは守るものであり、そこを曲げろと言っているのではないんです。統一した基準で判定して下さいと言っているんです。ルールブック通りなら「2秒以上5秒以内」を徹底してほしいだけだし、「完全停止」を求めるならそれをその大会に関わる審判員で統一して、監督会議あたりで説明しておいて欲しいだけです。
それを守れないピッチャーにはどんどん「イリーガルピッチ」を宣告して欲しいし、そのことが出来ないピッチャーは試合では投げられなくなるだけのことです。
問題なのは、その大本の「ルール」と「ケースブック」の記述が、曖昧な判断を許していることだと思います。
協会内でも、このことについては問題提起されていて、検討されているということですので早い是正をお願いしたいものです。すべての試合が公平なルールで実施されてこそ、本来の実力で勝負できることになります。
日本ソフトボール協会に期待しましょう。